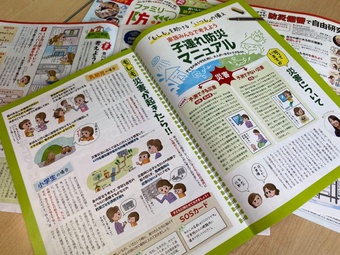本日”お姉ちゃん””になる花巻おもちゃ美術館オープンでした!
今日は岩手県花巻市のマルカンビル内に「花巻おもちゃ美術館」がオープンしました!
本当なら現地でお祝レセプションに参加しオープニングで子どもたちと一緒に木の香り一杯のおもちゃの中で遊びはじけている・・はずだったのですが・・・
あいにくコロナ再燃で、先週末に予定していた飛行機やホテルを泣く泣くキャンセル・・・。
レセプションにはZOOMでオンライン参加でお祝いの言葉を伝えました
そう。なんで遠方の岩手の出来事にこんなに私が盛り上がっているかって?
さぬき木のおもちゃ美術館(仮)の開館に向けて密かに準備レポートをアップしていることでもお分かりの通り・・・
わははネットも2022年オープンに向けて、姉妹おもちゃ美術館の準備をしています!!
東京おもちゃ美術館にはじまり、沖縄やんばるのおもちゃ美術館、山口県長門市のおもちゃ美術館、秋田県由利本荘市の鳥海山おもちゃ美術館・・・そしてこの度の花巻おもちゃ美術館
姉妹美術館としてこんなにあちこちに「お姉ちゃん」のおもちゃ美術館が出来て頼もしい!
そして、お姉ちゃんを見ながら育つ「妹(さぬききのおもちゃ美術館)」はお姉ちゃんに負けずに頑張らなくっちゃ!と想いをあらわにしております(笑)
それぞれの地域性がグググっと出て、その土地その土地の空気や自然を感じられ、地域の人たちが紡ぎだすおもちゃ美術館の独特の個性と子どもののみならず大人も癒され落ち着きそしてワクワクする空間・
ああ!早く行きたい!お姉ちゃんに会いに~~!
とにかく花巻おもちゃ美術館のオープンおめでとうございます!
お姉ちゃんの背中を追いかけ私も頑張るよ~!