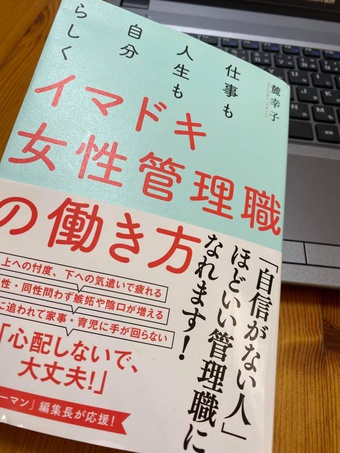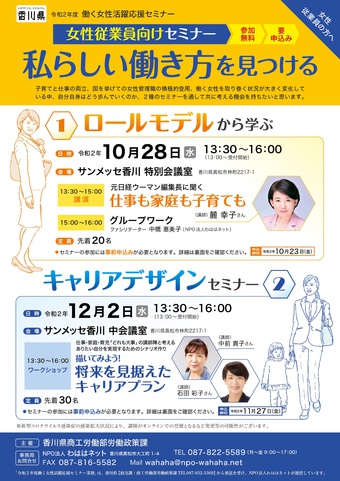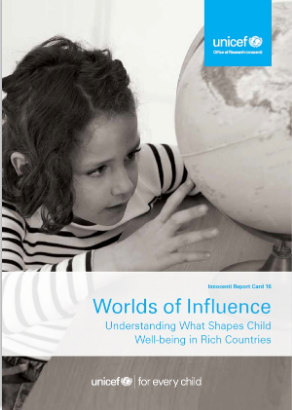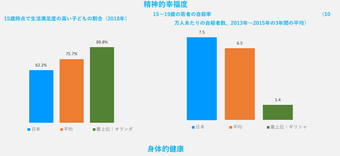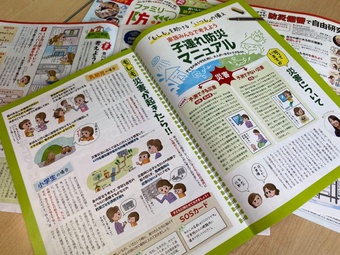昨日は高松市の子ども子育て支援会議でした。
事前に送られた資料にはしっかり目を通し予め意見書をドーンと送っているので(笑)、
それでもさらに会議ではしっかり資料をにらみつつ・・・
って文字が小さくて見えにくいんじゃ~~と、久しぶりにカバンに忍ばせている老眼鏡by百均を取り出したら・・・真ん中から真っ二つに折れているではないか?!
しかし私の心は折れずにまず・・・
乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)について生後4か月までの家庭に地区保健師や助産師等が訪問する事業だけれど、昨年度の対象者は3186人。そのうち訪問できたのは2944人
つまり242人のご家庭には訪問できていない
一昨年度も245人、その前も249人・・・とだいたい250人前後の家庭には訪問ができていないのが現状
理由は、里帰りからまだ戻ってきていなくて訪問が出来ないケースが多い。ということはこれまでも何度も質問してきたので知っている
でもこのコロナ禍で、様々なことがオンラインでトライされ始めており、この訪問事業も里帰り等の理由の方にはオンラインでの面接も大丈夫よ!という仕組みを作れば、少なくともご家庭からアクセスしてもらうことが可能な方にはご家庭の様子や赤ちゃんの様子も画面越しではあるけれど確認できるし、一度オンラインで面談しておけば顔が分かり、帰省後の実際の訪問受け入れのハードルが下がるのではないか?というご提案をさせていただいた
つまりは保健の分野でも対面が難しいシーンの場合にオンラインを有効活用していけばよいのではないかと。
だって、このコロナで今はさらに外部からの訪問を嫌がる人や、里帰り出産から戻れなくなっている人、また中には産後鬱等でメンタルの状況が芳しくなく外部の人を受け入れられない、あるいは虐待傾向が隠れているケースもあるかもしれない。
このタイミングで何らかの方法で産後家庭にアクセスすることはとっても重要で「242人訪問できてません」という報告をそのまま対策せずにそうですか、と受け入れることはできないのだ。
―――――――が、しかし委員のお一人は「子育ては抱いて触れてなんぼ。インターネットを活用しての子育て支援なんて」と反対意見をされた方がいらした。
たぶんインターネット使えない方なんだろうな、と思ったし、私は子育て支援のすべてをオンラインで、と言ったわけじゃなくうまく併用していけば、と提案したんだけれど。。。。
ちょっと残念。
まあコロナをピンチと捉えるかチャンスととらえるか
子育て支援の分野でも上手にオンライン活用をしてコロナがあったからこの仕組みが構築できた、とチャンスに変換できるかどうか、そんな柔軟性を行政に求めたいと思います