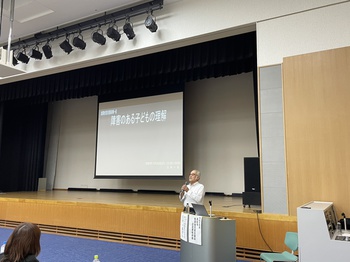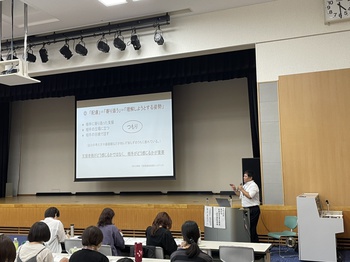【開催報告】令和6年度香川県ライフデザイン講座事業 高松中央・高松高校
香川県のライフデザイン講座事業は、県内の高校生に、国家資格キャリアコンサルタントや香川県助産師会が講義を行い、将来のライフデザインについて考える機会を提供するものです。
10月25日に高松中央高等学校、
10月28.29日、11月5.20日に高松高等学校で開催し今年度の全ての講座が終了しました。
2校では、キャリコンサルタントでもあるわははネットの副理事長小出から子育ての変遷や現代~これからの子育て、またライフデザインの考え方について、直接講義がありました。
そして、助産師会からはライフデザインを考える上で知識のひとつとして妊娠・出産には今の過ごし方や年齢が関係あることが動画で伝えられました。
限られた授業の時間の中で、生徒たちは時折メモを取りながら真剣に話を聞いていました。
そして、タイムマシンワークでは、
20年後のことを具体的に答えられる生徒、話しながら少しずつ鮮明になる様子の生徒、ペアを組んだ生徒からの質問に悩み答えが出てくるまで時間を要す生徒など、さまざまでした。
目の前の進学や就職のその先の未来に目を向けることは、簡単なことではないかもしれませんが、 “自分の将来のことを考える”それこそがライフデザインの第一歩であると小出から伝えられました。
今年度は県内5校、約830名の高校生に向けて開催してきました。
終了後のアンケートでは「初めて自分のこれからのことを友達に話したけれど、楽しかった!」という感想が聞かれました。
本講座がライフデザインを考えるきっかけになり、生徒たちが将来自身の望む自分になれるように、自分自身の選択に納得感を持って進むことができることを願います。